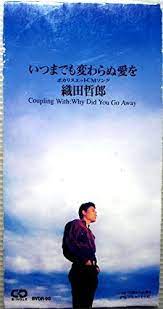おはようございます。
今日は織田哲郎の「いつまでも変わらぬ愛を」です。
ネットをチェックしていく中で、”ビーイングは日本のモータウンで、ベリー・ゴーディが長戸大幸、スモーキー・ロビンソンが織田哲郎”だと評していた人がいたようで、なるほど、と思いました。
確かにベリー・ゴーディも初期は曲を書いていたしな、などと思いつつも、長戸大幸は作編曲の仕事をたくさん手がけていて、音楽の作り手としての素養はゴーディよりもはるかにあったでしょうから、正確には、ベリー・ゴーディ=長戸、スモーキー・ロビンソン=長戸&織田、ホランド=ドジャー=ホランド=織田、じゃないか、と僕は思ったのですが、そんなことはどうでもいいですかね(苦笑。
ともかく、織田哲郎は日本の音楽史上、筒美京平、小室哲哉の次にセールスをあげている日本のポップス史に名を残す作曲家ですから、今回少し踏み込んで調べてみたいなと思いました。
1978年、長戸が発案した覆面ディスコ・バンド、スピニッヂ・パワーのボーカリストもやっていた織田は、長戸の実弟である長戸秀介、ギターの北島健二の3人で”WHY”というバンドでデビューを果たします。
ちなみに、長門と織田が出会ったのは、北島健二を通してだったようで、北島が舘ひろしのバックでギターを弾いていて、当時舘の曲を書いていた長門と知り合い、織田と長門を引き合わせたのだそうです。
WHYはシングル2枚、アルバム1枚だけを残して解散しますが、その後彼は、1980年に”織田哲郎 & 9th IMAGE”を結成します。
メンバーは、北島健二のほか、のちに浜省のバンドのサックス奏者になる古村敏比古やのちにBOØWYのベースになる松井常松、のちにバービー・ボーイズのドラマーになる小沼俊昭といったすごい面々が揃っていました。
”織田哲郎 & 9th IMAGE”は、実は、佐野元春や浜田省吾とほぼ同じ時期に、ブルース・スプリングスティーンっぽいスタイルを取り入れていたバンドなんですね。こういうスタイルは、1980年代半ばに尾崎豊や中村あゆみなどによって大ブームになりましたが、そのパイオニアの一人が実は織田哲郎だったのです。
現在もCD化はおろか配信もされていない「色あせた街」。同時頃にリリースされた佐野元春「アンジェリーナ」や浜省「終わりなき疾走」以上にスプリングスティーンに近いアプローチをしていると思います。
しかし、このバンドもうまくいかず、程なくして解散してしまいます。
そして2年ほど低迷期と呼べるような時期を過ごした後、1983年にソロデビューし、以降、1990年代前半までコンスタントにソロ作品をリリースしていきます。
そして、1985年のTUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」の大ヒット以降、彼は作家として売れっ子になっていきます。
他のアーティストの曲に数多くの曲を提供しながら、自身の作品も精力的に作っていきましたが、ソロ作品の方はなかなかヒットに恵まれませんでした。
当時はTVやラジオのレギュラーもやっていたそうで、そんな超多忙な日々の中で燃え尽きたのか、彼は一度音楽を辞める決意をし、実際一年近く仕事をしない時期があったそうです。そのあと、長戸から来たのが「おどるポンポコリン」でした。
「B.B.クィーンズのプロデュースやアイディア、戦略はすべて大幸さんが考えたものです。その大幸さんから依頼があって「ちびまる子ちゃん」用に当初2曲作っているんです。『おどるポンポコリン』と『ゆめいっぱい』という2曲を番組のオープニング用とエンディング用とセットで作曲・編曲し、オケの制作も担当することになりました。両極端な曲想だったけど、どちらもオケが出来上がるまでそれほど時間も掛からなかったし、楽しんであっという間に出来ました。」
(アスペクト 織田哲郎ロングインタビュー 2007.8.29)
そして、それをきかっけに音楽に再び真剣に取り組むなかで生み出されたのが、彼のソロ・アーティストとしての初の大ヒット曲である「いつでも変わらぬ愛を」でした。
「音楽によって救われる人が世の中にいて、自分の作る音楽が人の悲しみを癒したり、誰かの心を励ましたり、苦しみをやわらげることに少しでも繋がるのであれば、それはとても意味のあることだし、もしそれが俺に出来るのであれば、音楽は作り続けるべきだと考えた。だからこの曲は「これからもう一度しっかりと音楽を届け続けます」という決意表明みたいなものです」
(アスペクト 織田哲郎ロングインタビュー 2007.8.29)
その翌年、彼が作曲したZARDの「負けないで」「揺れる想い」、中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」、DEENの「このまま君だけを奪い去りたい」といった、曲名をサビで印象強く伝えるという”ビーイング・スタイル”の先駆けになった曲だったことに気づきます。
そして、オープニングのサックスに、彼がデビュー当初に打ち出したスプリングスティーン・スタイルへのオマージュを少し感じてしまいます。
さて、織田哲郎はネット・インタビューが割と多くあって、彼のベースとなった音楽についても興味深い発言がいくつかありました。
「一番聴いたのはサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」(1970年)というアルバムで、どの部分でどの楽器が出てくるということまで、記憶しています。結局それがアレンジ能力に繋がってくるわけです。こういうところでこういう音がこうやって出てくると、興奮するよねって、何百回何千回聴いてるものが実体験として、脳に叩き込まれている。そうやって同じものを聴き続けるってこと、例えば野球でいう、素振りとか基本のフォームを作るというような部分は、やっぱり重要だと思います」
(SPICE インタビュー 2019.10.11)
「実は小学生の頃から自殺願望があったんですよ。高知の寮で、いよいよ本当に自殺を決行しよう、と思って刃物とラジカセを持って屋上に上がった。好きな音楽聴きながら死のうと思って。その時選んだのはの「Your Song」や「ロケットマン」という曲が入ったベストアルバムのようなカセットテープだった。そのギリギリの精神状態のなかで聴いたエルトン・ジョン、これがその後の俺を変えた…。その時音楽が全部光に変換されて、俺の頭の中をものすごい勢いで洗い流していったんです。涙が止まらなくなった」
(アスペクト 織田哲郎ロングインタビュー 2007.5.30)
「明日に架ける橋」にエルトン・ジョンのベスト。音楽的なクオリティと大衆性の両面のバランスという意味でまさに最高峰の作品ですよね。ポップスのソング・ライターの糧としては究極のものでしょう。それが、彼には強く刻まれているわけです。
織田哲郎は”王道”、いたって”正統派”のソングライターなのでしょう。そして、捻りや屈折があまり感じられないから、ポップス・マニアの話題にはあまり上がらないのかな、とも思います。
しかし、洋楽のポップスを、日本語の発音や語感にぴったりなフォームにしっかり変換させた才能はもっと評価されてもいいなと思います。それには、相当”音楽的な体力”が必要なことなのだと思うんです。
彼の曲からは、”簡潔な言い回しの文章を、太字の読みやすいフォントですっきりしたレイアウトで送られてくるメール”のようなを印象を受けます。
ただ、それを音楽でやると、並みの才能では、ただただ淡白で味気ないものになりかねないような気がします。
音楽の普遍性にふれるような優れたインプットと、様々な試行錯誤をして鍛えられたアウトプットの技術の両面がないと難しいんじゃないかと思います。
でも当時の僕は正直言ってビーイングのポップスを”誰でもすぐに作れそうなものじゃん”となめていたところがあったんですね。
今は、シンプルでわかりやすく、それでかつ大衆の心をつかむもの、というものこそ難しいということがよくわかります。
そこには、日本語のポップスというものの本質を突いたものもあるような気がします。洋楽っぽいポップスをやる場合、桑田佳祐や佐野元春のように日本語と英語を混ぜ合わせたり、英語っぽく発音したりすることが流行った時代がその前にありました。そして、それが流行ったがために、ダサい使い方をする歌詞がどんどん増えていったんでうしょね。
そこで、ビーイングは洋楽っぽいサウンドでも歌詞は日本語でほぼ完結するスタイルを打ち出していったわけです。
それは誰でも歌いやすい、という長所がありますから、そのビーイングのスタイルは、当時のカラオケ・ブームとの相性がバッチリだったわけです。それも当然計算していたのかもしれません。そして、そのスタイルは織田哲郎なくして完成しなかったのではないかと思います。
詞曲の才能があるだけでなく、声量のある個性的な歌声も持ち、ルックスも決して悪くない彼が、アーティストでなく、作曲家で成功したのは少し不思議な気もしますが、それは彼のキャラクター、気質によるものだったのかもしれません。
「俺は、昔からクラスの人気者になるよりも、職人的にコツコツとモノつくりすることが好きだったんだと思います。高校時代にバンドを組んだときもボーカルには興味がなくて、ギターを弾いて曲作りに専念したいと考えていました。俺にとって、人に曲を提供するのは単純に楽しめる仕事なんですよ。ターゲットを想定しながら作っていく過程は、ゲームみたいな要素もありますから。単にヒットするだけじゃなく、歌手やアーティストの存在を大きくする作品を書くことが理想ですね」
(「J・POP名曲事典300曲」富澤一誠)
ちなみに、ZARDは長戸大幸が買ったベンツのランプに書いてあった「HAZARD」の文字がかっいいと思ったのがきっかけでつけられたものなのだそうです。
曲はもともと織田が自分用に書いたもので、そのサビに「負けないで」というフレーズをZARD(坂井泉水)本人が見事にはめたことで、この曲がヒットしたのだと織田は語っています。
ちなみに、当時ビーイングの方針で、作曲家はアーティストに直接会えなかったようで、織田はZARDに多くの曲を書きながらも本人には2度しか会ったことがなかったそうで、それにはちょっと驚かされます。
<広告>